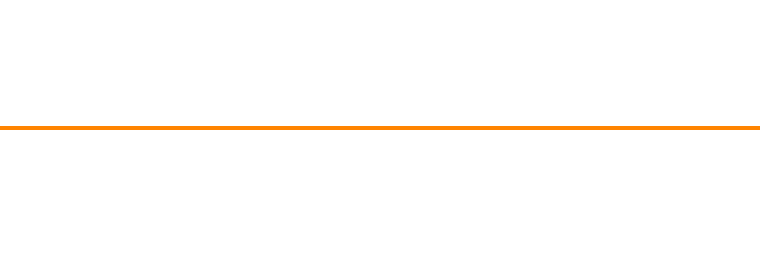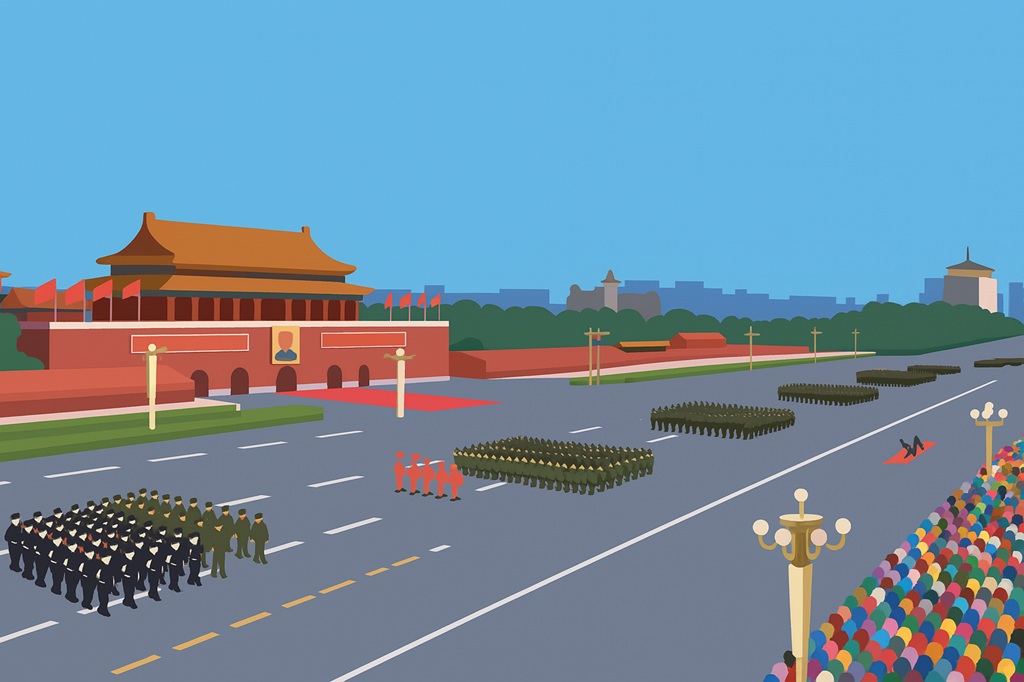香港メディアの
頭条日報によると、北京大学海洋研究院の南海戦略態勢感知計画(SCSPI)は16日、ツイッターで、米空軍の偵察機RC135S「コブラボール」が、浙江省寧波市の沖20カイリ(約37キロ)に接近したと発表した。米軍偵察機の中国本土への接近距離としては、過去最短となった。(写真は頭条日報のサイト画面)
SCSPIが公表した人工衛星画像によると、米軍偵察機は16日未明に沖縄の県嘉手納空軍基地を離陸、東シナ海に向かった。同日午前4時、寧波沖に到着し付近の飛行を続けた。RC135Sは今月1日にも、中国の東シナ海の防空識別圏を飛行し、偵察を行った。
SCSPIは米軍の重要な偵察機で、通信や電子、ミサイルなどの関連情報を収集している。これまで中国の海岸線から50~70キロ離れた距離を飛行するが通例だったが、今回、異例の近距離を飛行した。米軍が、偵察の内容をさらに深めている可能性がある。
○米駆逐艦が台湾海峡航行 バイデン政権で5回目

香港メディアの
頭条日報によると、北京大学海洋研究院の南海戦略態勢感知計画(SCSPI)は16日、ツイッターで、米空軍の偵察機RC135S「コブラボール」が、浙江省寧波市の沖20カイリ(約37キロ)に接近したと発表した。米軍偵察機の中国本土への接近距離としては、過去最短となった。(写真は頭条日報のサイト画面)
SCSPIが公表した人工衛星画像によると、米軍偵察機は16日未明に沖縄の県嘉手納空軍基地を離陸、東シナ海に向かった。同日午前4時、寧波沖に到着し付近の飛行を続けた。RC135Sは今月1日にも、中国の東シナ海の防空識別圏を飛行し、偵察を行った。
SCSPIは米軍の重要な偵察機で、通信や電子、ミサイルなどの関連情報を収集している。これまで中国の海岸線から50~70キロ離れた距離を飛行するが通例だったが、今回、異例の近距離を飛行した。米軍が、偵察の内容をさらに深めている可能性がある。
○米駆逐艦が台湾海峡航行 バイデン政権で5回目