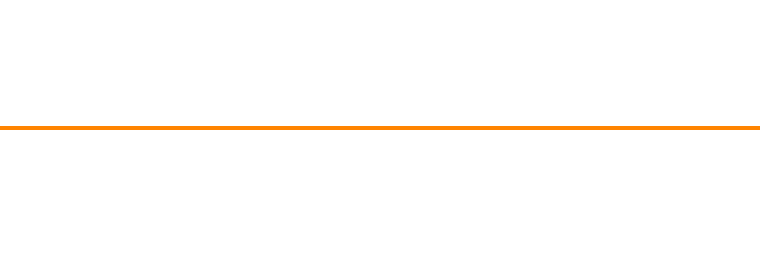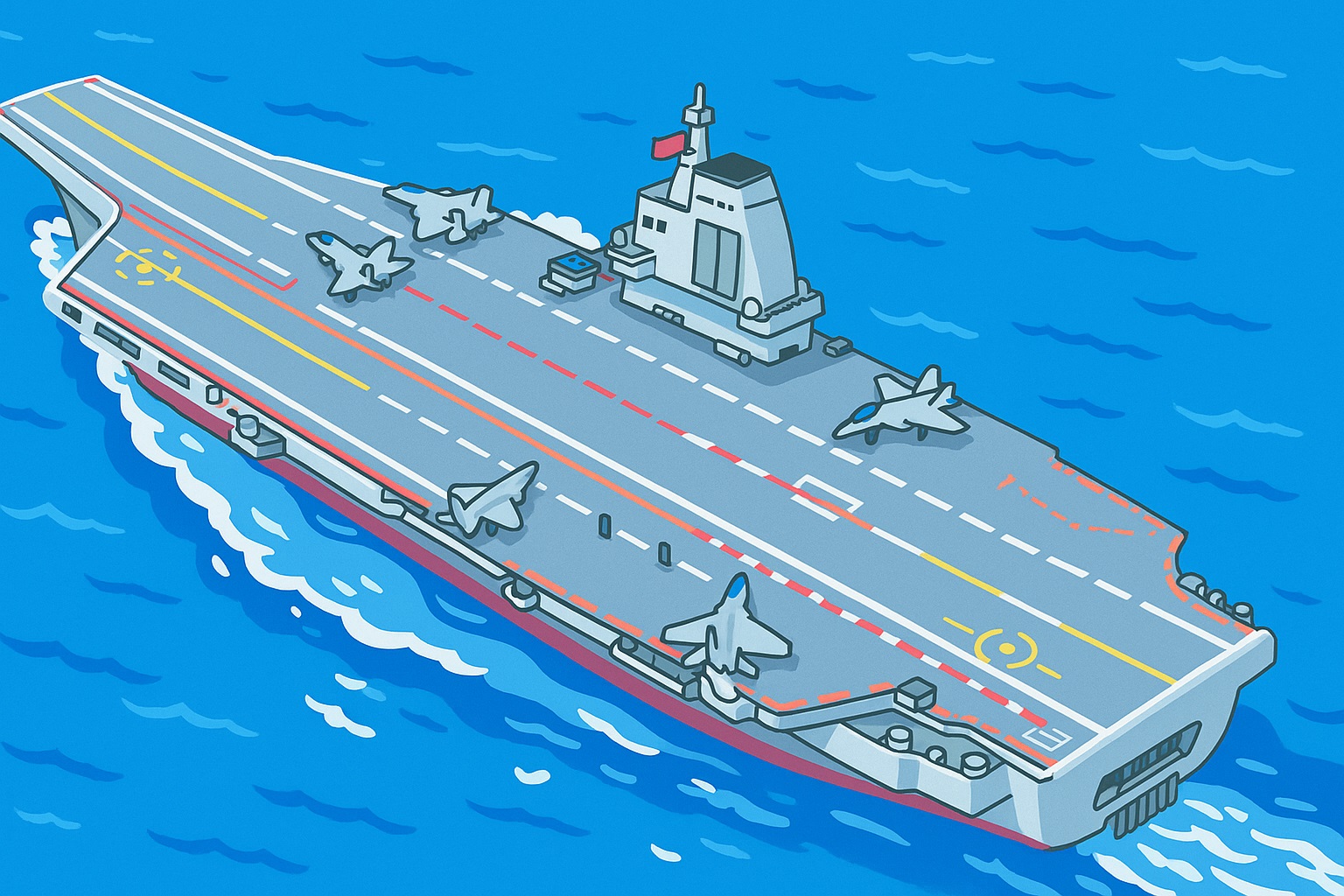中国海軍の冷国偉報道官は8日、空母「福建」が5日に海南省三亜の軍港で就役したと発表した。福建艦は中国初の電磁カタパルト搭載型空母であり、現役艦艇として最大排水量を持つ。戦備需要、港湾条件、後方支援能力、任務特性を総合的に判断し、常駐地を三亜軍港とする方針を明らかにした。
三亜の楡林港は空母運用向けに整備された大型軍港で、中国の空母母港は大連、青島、三亜の3カ所に分かれる。福建艦が三亜に配置されることは、南シナ海や台湾海峡情勢に対する戦略的重心がいっそう南へ移ることを意味する。
(内部リンク)
- 空母「福建」が三亜で就役目前 習主席が海南入りし最終調整
https://www.alertchina.com/post-33470/
福建艦が備える電磁カタパルトは、中国海軍の空母運用を大きく変える技術だ。これにより、艦載機の発進効率の向上、機体寿命の延伸、重量級の早期警戒機や無人機の発艦が可能となる。冷国偉は、殲35、殲15T、殲15D、空警600、直20シリーズなどの艦載機・支援機の開発と試験が計画通り進んでいると述べ、完全編成での搭載も遠くないとした。
電磁カタパルトを用いた運用は今回が初となるため、就役後も試験航行や装置検証を継続し、システムの安定性を検証する段階が続く。中国は艦と航空機の適合訓練、編隊体系の訓練を段階的に拡大し、実戦能力を高める展望だ。
(内部リンク)
- 空母「福建」、就役迫る 電磁カタパルト発着艦成功
https://www.alertchina.com/post-32978/
南シナ海・台湾海峡・西太平洋への影響
中国国営メディア「玉淵譚天」は、福建艦が今後向かう海域として台湾海峡、南シナ海、西太平洋を挙げた。さらに東太平洋、インド洋、大西洋への進出も必要だと指摘し、グアム、ハワイ、豪州付近の海域を具体例として示した。
中国はこれら海域で航行する権利が国際法に基づくものだと主張しており、米軍の前方展開拠点と重なる地域で空母の影響力が強まる可能性がある。福建艦の三亜常駐は、域内の戦力配置に直接影響するため、西太平洋の戦略バランスを変える要因になり得る。
(内部リンク)
- 【特集】中国の最新空母「福建」就役間近 台湾海峡通過で3空母体制へ
https://www.alertchina.com/featured/featured-32856/
大連の遼寧艦、青島の山東艦、そして三亜の福建艦。この3空母体制が確立すれば、中国は北海・東海・南海の3方面で同時運用が可能となる。特に福建艦は遠洋向けの設計思想が強く、外洋展開能力の強化が中国海軍の今後の重点になるとみられる。
福建艦は新技術を多数搭載しているため、短期的には訓練負荷が大きいものの、中期的には中国海軍の作戦範囲を西太平洋からインド洋へ拡大する軸となる。
(内部リンク)
- 中国、新型空母「福建」南シナ海で試験航行
https://www.alertchina.com/post-32836/