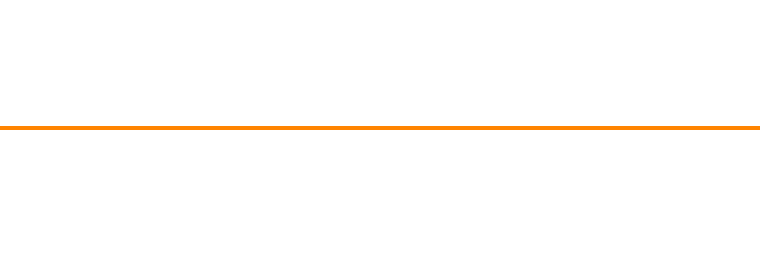給水所で物資持ち去り騒動 大会後に混乱広がる
2025年10月26日に行われた成都マラソンの終了後、沿道の給水所に残っていたミネラルウォーターが周辺の市民に大量に持ち去られる事件が発生した。ネット上に投稿された映像では、中高年の男女が未開封のミネラルウォーターの箱を次々に抱えて持ち出す姿が映り、スタッフが「持っていかないで!」と叫んで制止するものの、止まる様子はなかった。
SNS上では「成都の大爺大媽が水を奪い合った」といった投稿が広がり、社会的な関心を呼んだ。映像では大会スタッフの制止の声がむなしく響き、物資が一斉に運び出される様子が生々しく記録されている。
大会後の現場は片付け作業中で、ボランティアや審判員が残っていた。あるボランティアは「見物していた人たちが突然物資を持ち出した。止めても聞かず、まるで早い者勝ちのようだった」と語った。別のボランティアは「バナナやパンなどの補給食も箱ごと持ち去られ、電動バイクで運ぶ人までいた。医療用品まで持ち出されそうになった」と証言した。
主催者が警察に通報 公安当局が調査を開始
10月28日、上游新聞の取材に対し、成都マラソンの主催者は「すでに警察へ通報し、確認と処理を終えた。今後は公安当局が介入する」と説明した。大会側は関連動画を確認しており、被害の範囲を調べているという。
主催者によれば、現場の詳細についてはまだ確認中で、「公安からの通知を待つ」としている。
今回の事案は、成都という大都市で行われた国際的イベントにもかかわらず、観衆による物資略奪が公然と行われた点で注目を集めた。
事件の映像は微博(Weibo)など中国SNSで瞬く間に拡散し、国内外のメディアも報道。大会運営側は、今後のマラソン運営における警備や物資管理体制の見直しを迫られている。
中国各地で頻発する「公共マナー崩壊」現象
成都マラソンの事例は、中国各地で近年頻発する群衆による略奪・盗難トラブルの一環とみられる。
例えば、洪水被災地で住民が救援物資を奪う事例が報告されており、広東省の地方都市では【洪水の地方都市で略奪被害 菓子や現金奪われる】という事件も発生している。
また、河南省では【野外音楽フェスで村民が大挙窃盗=テントや車も―河南】、【トウモロコシ畑を村民が大挙襲撃=収穫物奪取―河南】など、集団による略奪行為が繰り返されている。これらの事件に共通するのは、「公のものは誰のものでもない」という意識の希薄さだ。
今回の成都マラソンでの物資持ち去りは、その象徴的な一幕として社会問題化しつつある。
背景にある社会的課題と運営上の問題
専門家の間では、こうした現象の背景に「公共意識の欠如」と「イベント運営体制の脆弱性」があると指摘されている。
中国ではマラソン大会が近年急増し、都市ブランド向上の手段として注目を集めているが、運営面ではボランティア教育や観客管理が追いついていない。
特に大規模イベントでは、給水所や補給地点の管理責任が曖昧になりやすく、残留物資を「不要品」と誤認して持ち帰る市民が出るケースもある。だが、主催側が明確に「大会資材であり私物化は窃盗行為」と周知しなければ、同様の事件は再発しかねない。
公安当局の調査結果次第では、法的責任の所在が問われる可能性もあり、イベント管理の制度化が今後の課題となる。
社会的モラルの再構築が求められる
成都マラソンで起きた物資略奪事件は、単なる一過性のトラブルではない。急速な都市化と社会の多様化が進む中国で、公共空間における「共の意識」をいかに育むかが問われている。
大会運営側だけでなく、参加者・観客を含む社会全体のモラル向上が求められている。スポーツイベントは都市文化の象徴であり、今回の事件を契機に「公共財の尊重」という意識改革が進むかどうかが注目される。
[出典]
[関連情報]