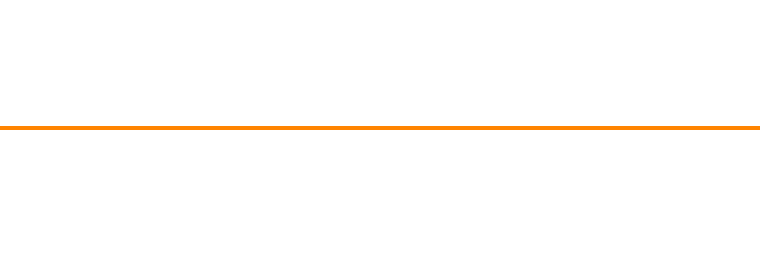中国国家統計局が15日に発表した9月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比0.3%下落し、2カ月連続でマイナスとなった。家計支出の低迷や不動産市況の不振が影響し、内需の回復が遅れている。米中摩擦の再燃や若年層失業の増加も重なり、デフレ圧力が一段と強まった。
物価下落の背景に消費停滞と構造問題
国家統計局によると、9月のCPIマイナス幅は8月(-0.4%)より小幅だったが、依然として予想(-0.2%)を上回った。1〜9月の平均は0.1%減。董莉娟主任統計官は、前年の「翹尾」効果がマイナス0.8ポイント、新たな変動要因がプラス0.5ポイントと説明した。
豚肉が17%、野菜13.7%、卵13.5%、果物4.2%と食品価格の下落が続いた。エネルギー価格も2.7%低下。一方で食品とエネルギーを除いたコアCPIは1.0%上昇し、19カ月ぶりに1%を超えた。
米紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、北京当局の価格競争抑制策や消費補助政策の効果が見え始めたと指摘したが、「内需は依然として力強さを欠く」と分析している(RFI報道)。
生産者物価指数(PPI)も前年同月比2.3%下落とマイナスが続き、8月(-2.9%)からは改善したが、依然として企業の収益を圧迫している。格付け会社・東方金誠の馮琳氏は「過当競争抑制策や景気下支え策の効果で第4四半期にはマイナス2%以内に収束する」と見通す。
政策効果に限界、内需喚起へ焦点
IMFは14日、中国に対して「財政政策を通じた消費主導型成長への再均衡」を求めた。若年層の高失業率や住宅市場の停滞が消費を抑制し、家計は将来不安から購買を先送りしている。こうした傾向は「通縮スパイラル」への懸念を高めており、当局の金融緩和や減税政策にも限界が見え始めている。
不動産市場の構造不況が消費回復を阻むとの見方も強い。中国では約20社の大手デベロッパーが再建中で、総債務は12兆元に達する(AlertChina:経営再建中の不動産開発会社20社、債務12兆元)。
政府は消費財の買い替え支援や補助金政策を強化しているが、景気浮揚効果は限定的だ。とりわけ地方政府の債務圧力が強まる中、財政余力が乏しい地域では実施に遅れが出ている。
四中全会控え官製メディアが「経済光明論」
こうした中、中国共産党は20〜23日に北京で第20期中央委員会第4回総会(四中全会)を開く予定である(AlertChina:第20期四中全会、10月20日開幕へ)。
会議を前に、官製メディアは「経済の強靭性と活力」を強調する報道を相次いで発信している。人民日報は7日連続で経済擁護の論評を掲載し、「外部環境の変化にもかかわらず、中国経済は安定した回復軌道にある」と主張した(AlertChina:人民日報が7日連続で経済擁護論評)。
共産党機関誌『求是』も15日付で、「市場の予測が弱く、企業経営者の信頼が不足している」と指摘。「経済宣伝と世論誘導を強化し、中国経済の光明論を全方位で唱えるべきだ」と主張した(聯合報)。
また、社会保障への不安が消費抑制を生んでいるとし、政府に「予測管理と心理安定化」を求めた。
市場心理と実体経済の乖離
政府発表と民間の景況感には温度差もある。日本貿易振興機構(JETRO)の調査によると、在中日系企業の4割が「景況感が悪化」と回答しており、安全保障や政策不透明性を懸念する声が強い(AlertChina:在中日系企業の4割「景況感が悪化」)。
こうした市場心理の冷え込みが、当局の「光明論」と対照的な現実を浮き彫りにしている。
中国政府は、経済政策の信頼性と一貫性を強調し、景気安定のための「政策調和」を掲げるが、民間の投資・消費心理を左右する要因は多い。今後、四中全会で示される経済方針が、どこまで実体経済の再活性化につながるかが焦点となる。
外部リンク(External)