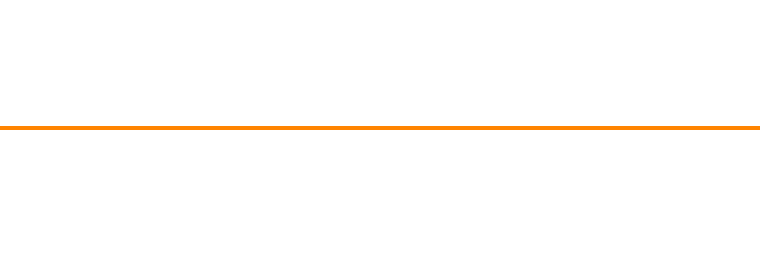情報収集リスク
中国で日本人の拘束が続く中、中国日本商会の本間哲朗会長(パナソニックホールディングス副社長)は「外部組織から委託を受けて情報を収集し、その成果を提供して報酬を得れば、情報内容を問わず《反スパイ法》に抵触する可能性がある」と警告した。日本人ビジネス関係者に対し「情報活動に巻き込まれないようにすべきだ」と強調している。
報道によれば、中国は2014年の反スパイ法施行後、少なくとも17人の日本人を拘束し、そのうち9人は日本の公安調査庁に情報を提供し報酬を得たとしてスパイ行為と認定された。本間氏は「事実なら極めて遺憾だ」と述べ、日本商会として日本政府に立場を示すよう求めた。
企業の対応
パナソニックは「外部組織から情報収集を依頼された場合は即時報告し、原則として受けない」と社員に通知。商会の他会員企業も同様の方針をとるようになった。
2025年7月には、アステラス製薬の社員で日本商会の元副会長が中国でスパイ活動に問われ、懲役3年6か月の判決を受けた。本間氏は「外部組織と接触せず、軍事施設を撮影せず、通常の商業活動を行う限り拘束リスクは低い」とする一方で、「報酬と成果を交換する形で依頼を受ければ、どのような情報でも違法と認定されかねない」と指摘する。
日本人襲撃事件
安全上のリスクはスパイ疑惑だけにとどまらない。2023年6月には江蘇省蘇州市で日本人母子が襲撃され、同行の女性ガイドが刺殺された。同年9月には深センで日本人学校の男子児童が刺殺され、2025年7月にも蘇州市で日本人母親が襲撃され負傷する事件が発生した。
こうした事件は、在中邦人の生活環境が以前より厳しくなっていることを示す。関連して alertchina.comの関連記事(「九一八事変94周年を前に蘇州でまた日本人襲撃」など) でも、在中邦人の治安リスクが繰り返し指摘されている。
投資と交流
本間氏は「我々は中日経済交流を促進するために中国に来ており、情報収集は任務ではない」と説明する。だが、事件や拘束が相次ぐ現状では、日本企業の駐在体制見直しが進み、家族を帯同しない赴任者や、先に帰国させるケースが増えている。
実際に、中国本土の日本人学校の生徒数は過去1年間で1割以上減少した。中国当局も7月の蘇州事件を受けて全国の日本人学校の警備を強化したが、不安は依然根強い。投資持続には「安全確保」が大前提であるとの認識が広がっている。