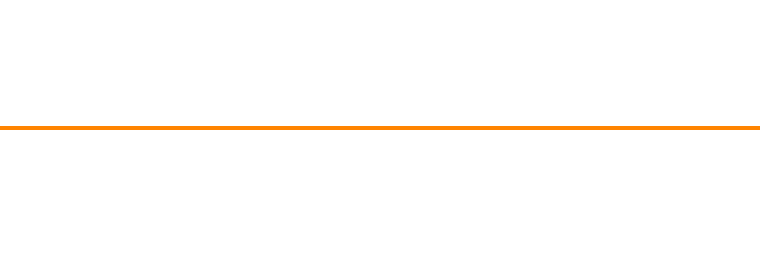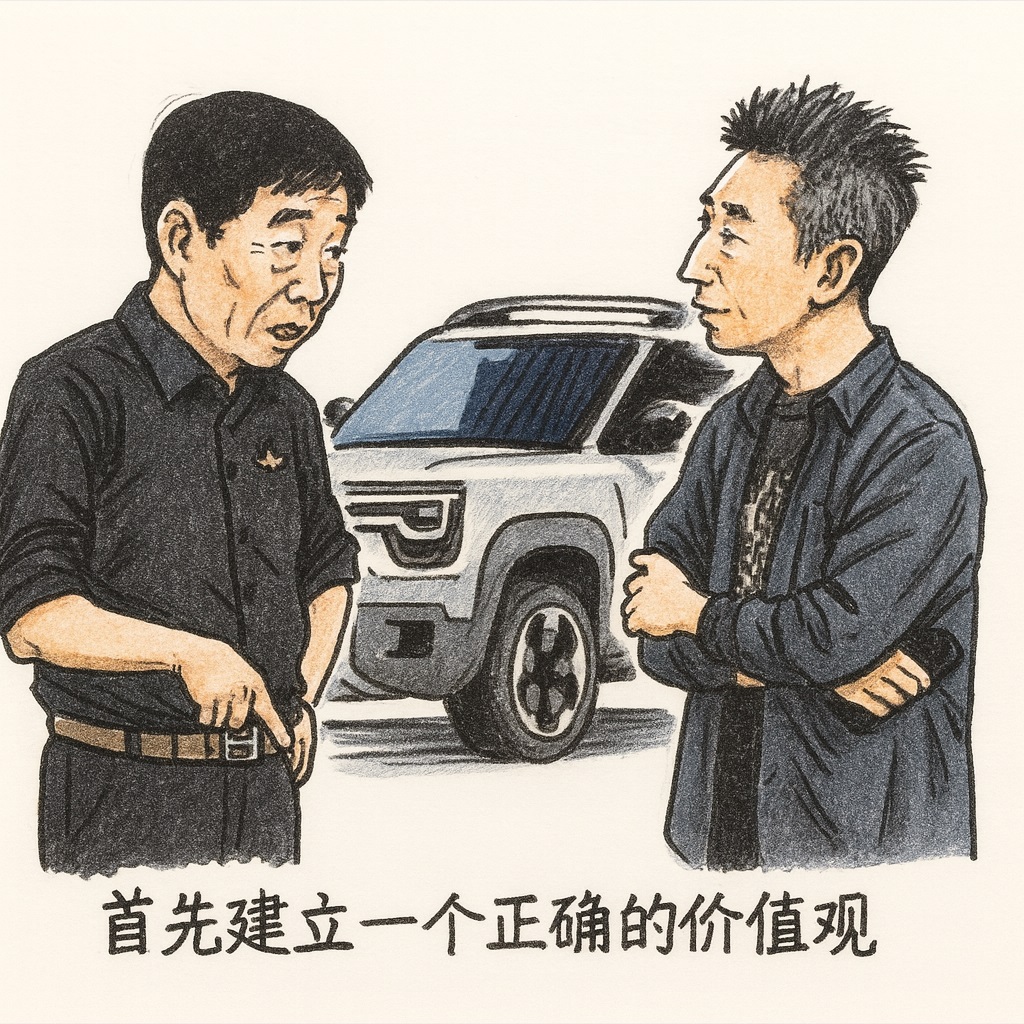
「小型はEV・大型はハイブリッド」
中国自動車業界で、これまで国策として推進されてきた「全面電動化」路線に見直しの動きが出はじめている。これまで政府はEV(純電動車)を中心に政策支援を続けてきたが、業界の中からは“EV一辺倒”への疑問の声が出始めた。その先頭に立つのが、長城汽車の魏建軍董事長である。
魏氏はインタビューで「小型車はEV、大型車はハイブリッドが望ましい」と述べた。ハイブリッドは技術的に難しいが、先進的なシステムが普及すれば使用コストはEVと大差なく、資産価値の維持率も高いという。EVを万能とみなす風潮に冷静な視点を投げかけた形だ。
また、「EVは小型化すべきだ」と繰り返し指摘し、「速度や大型化ばかりを追い求めるのは方向を誤っている」と批判。中国市場で広がる“大型・高出力志向”に対し、構造的な見直しを促した。
「内燃機関・ハイブリッド・EV・水素、すべて発展すべき」
魏氏はEVに限らず、複数の動力技術を総合的に発展させるべきだとの立場も明確にしている。
自動車情報サイト「Autohome(汽車之家)」によれば、魏氏は「内燃機関、ハイブリッド、EV、さらには水素も発展させるべきだ」と述べ、特定の動力形式に依存しない「総合的発展論」を示した。
さらに、テック系メディア「前瞻網(Qianzhan.com)」は、魏氏が「EVは主流にはならない。複数の動力が共存するのが理性的だ」と発言したと報じている。
これは「併存型戦略」と呼べる方向性を示すものであり、政府の電動化方針に対して市場実態に即した柔軟な視点を提示したといえる。
直言居士の魏氏、昨年は「中国EVに核心技術なし」で波紋
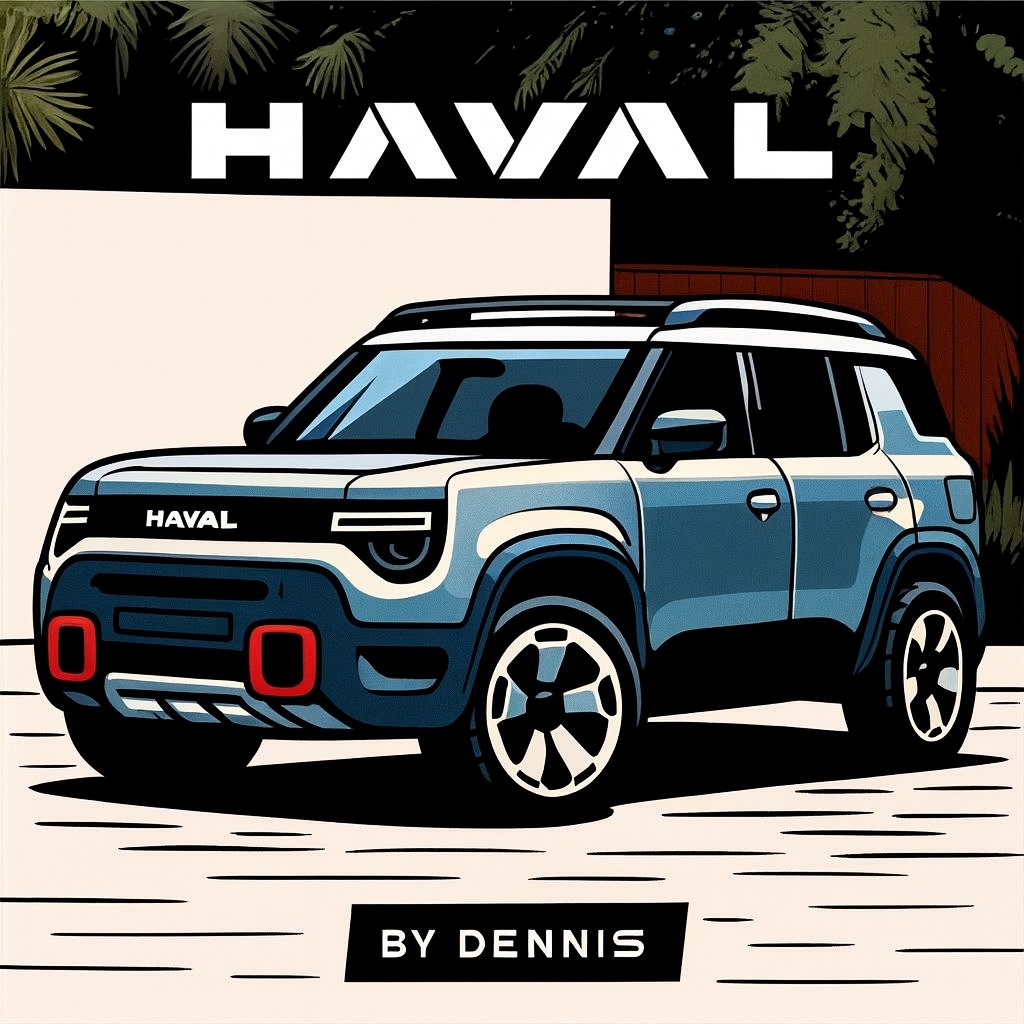
魏氏は率直な発言で知られる経営者だ。2024年10月には「中国の電気自動車は核心技術で優位に立っていない」と発言し、業界に大きな波紋を広げた。
専門家は「中国の自動車メーカーに核心技術がないというのは誤りだ」と反論したものの、「各社が似たような技術を共有しており、他社を寄せつけない独自性が乏しい」と述べ、結局、魏氏の指摘を追認している。
さらに、2025年6月には、魏董事長は比亜迪(BYD)を名指しこそしなかったものの、「すでに車業界における“恒大”的存在は現れている」と発言。これを受けて一部メディアが「BYDは次の恒大」と報道したことで、BYDが即座に反発する騒動となった。
BYD側は「健全な財務と生産体制を有しており、根拠のない中傷だ」と強く否定し、長城汽車との関係も一時的に緊張したとされる。
詳細は以下の記事を参照。→ 中国車会社トップ「BYDは次の恒大」 BYDは反発
魏氏はその後も、モーターや制御チップなど多くの部品が依然として海外製である現実を指摘し、「中国の強みは産業チェーンにあるが、基礎技術ではない」と述べている。今回2025年9月の発言は、そうした現状認識を踏まえた延長線上にある。
ただ、今回は中国政府系メディアの中国中央テレビのインタビューに応える形で見解を明らかにしたもので、EV一辺倒からの脱却は、当局の方針転換を代弁している可能性がある。
誇大宣伝にも警鐘 「正しい価値観が成長の道」
魏氏は自動車業界の誇大宣伝にも苦言を呈している。
「物理的限界を超えた性能をうたいながら、実際にはブレーキすら効かない車がある」と述べ、実力以上の宣伝を戒めた。
長城汽車では、発表会などで誇張した表現を行った幹部を処分・反省させる方針を打ち出し、「正しい価値観を築き、実直に差を埋めることが成長への道だ」と強調した。
魏氏はまた、「支払いを長期間遅らせても資金コストが膨らむだけで意味がない」と述べ、長城汽車は中国自動車工業協会が9月に打ち出した代金支払い規範の順守を宣言。電信送金や銀行手形など、現金決済に近い支払い方法を徹底する方針を打ち出した。中小サプライヤーの保護を目指す。
BYDも複線戦略へ 「多動力共存」が新潮流に
他のメーカーからも、EV一辺倒を見直す動きが出ている。電池・自動車メーカーの比亜迪(BYD)は欧州市場でハイブリッド車の販売を拡大しており、燃費効率を高めた新型モデルを投入。地域や用途に応じてEVとハイブリッドを併用する“複線戦略”を進めている。BYDは、もともとガソリン車のメーカーで、新興のEV勢力とは異なり自動車製造の経験が豊富だ。
収益構造の多様化も狙い
中国EV市場は成長鈍化と価格競争の激化に直面している。
バッテリーコスト上昇や充電インフラ整備の遅れもあり、企業は収益構造の多様化を迫られている。
魏建軍氏の一連の発言は、現実に即した「電動化一極からの離脱」を示唆するもの。今後、中国自動車メーカーは、プラグイン・ハイブリッド(PHV)やレンジエクステンダー式電気自動車(EREV)のウエートを高める可能性が高い。