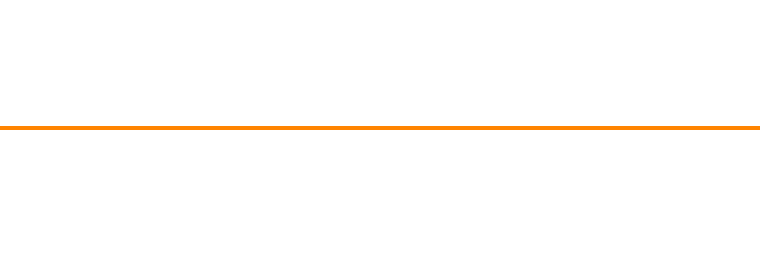中国政府は11月19日、日本政府に対し日本産水産品の輸入手続きを停止すると正式に通知した。発端は11月18日の衆議院予算委員会での高市早苗首相の「中国が台湾を武力封鎖すれば存亡危機事態となり得る」との発言で、中国側は強く反発した。台湾の聯合報(出典1/出典2)などが報じた。
日本産水産品の禁輸はこれが二度目となる。中国は2023年8月24日、福島第一原発の処理水海洋放出を理由に全面停止を実施していた。今年5月31日には輸出再開条件について両国がいったん合意したが、施設登録は実質進まず、697施設の申請のうち承認は3施設のみと停滞が続いていた。
さらに中国政府は日本への渡航・留学にも制限を強化し、航空券の大量キャンセルが相次ぐなど、対日圧力を広範囲に拡大している(中国で日本旅行キャンセルが急拡大)。
ホタテ産地は輸出多角化が進展 「衝撃は限定的」との見方が主流に
一方で、日本の水産業界では今回の輸入停止による影響は限定的とみる声が強い。理由は、2023年の禁輸以降、すでに中国依存からの脱却が大きく進んでいたためだ。
北海道のホタテ産地では、2023〜2025年の禁輸期間中に米国・欧州連合向けの販路開拓が加速した。2025年11月中旬の噴火湾初入札では、ホタテ価格が前年同期比8割高となり、海外需要の強さが確認された。
加工工程では自動殻むき機の導入が進み、中国の加工工場への依存度は大幅に低下した。こうした産地の構造転換により、2023年当初の滞留・価格暴落のような混乱が再発する可能性は小さいとみられる。
業界関係者は「対中輸出の不安定さは織り込み済みで、市場多角化は不可逆的だ」と語り、冷静な受け止めが広がっている。専門家も「水産物を内需で吸収できる産業構造への転換が課題だ」と指摘する。
「台湾有事」発言と中国の対日圧力 水産物禁輸は外交カードか
今回の輸入停止は、政治問題を経済措置に転換する中国の典型的な対外手法とされる。人民日報は高市首相を名指しで批判し、対日非難を強め(人民日報、高市首相発言を異例の全面批判)、外交圧力は連日拡大している。
航空・旅行・文化交流の分野でも制限が相次ぎ(中国が対日制限を一斉強化)、日中関係の緊張は国内外の幅広い領域に波及している。
日本国内では「次はレアアースが対象になるのでは」との懸念が出る一方、「中国の経済圧力に屈してはならない」との支持論も根強い。水産品禁輸は、日中関係が長期的に緊張局面に入る中での象徴的措置として位置づけられる。
[出典]
・https://udn.com/news/story/6809/9153628
・https://udn.com/news/story/7331/9150931
・https://www.stheadline.com/realtime-china/3519865
[関連情報(内部リンク)]
・https://www.alertchina.com/post-33594/
・https://www.alertchina.com/post-33583/
・https://www.alertchina.com/post-33586/
・https://www.alertchina.com/post-33574/
・https://www.alertchina.com/post-33558/
・https://www.alertchina.com/post-33563/