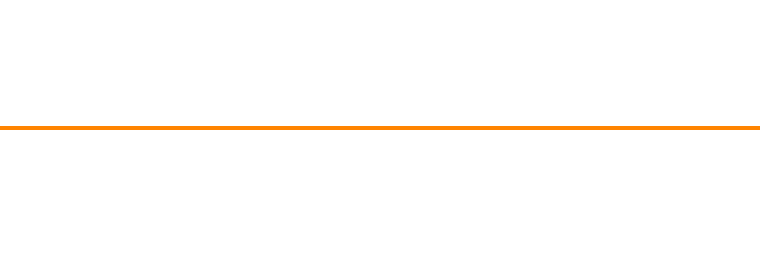自衛隊幹部が北京入り 9日間の日程で中国軍施設を視察
自衛隊の佐官級幹部約10人が11月5日に北京へ到着し、9日間の訪中プログラムを開始した。訪問は13日まで続き、北京市、広東省、湖北省で中国人民解放軍の陸・海・空軍関連施設を視察するほか、中国軍系シンクタンクである中国国際戦略学会と交流を行う。台湾中央通信社および香港メディア東網が相次いで報じた。
今回の派遣は、高市早苗首相と習近平国家主席が10月末に韓国で初めての首脳会談を行い、防衛当局間の危機管理と実効性ある意思疎通の重要性で一致したことを受けたものだ。
高市首相を巡っては、APEC会議で台湾代表と会談したことが中国側の反発を招き、日中共同世論調査の発表延期にも影響した可能性が指摘されている(関連:「日中共同世論調査の発表延期」 https://www.alertchina.com/post-33442/、 「高市首相が台湾代表と会談」 https://www.alertchina.com/post-33434/)。
2001年開始の軍事交流事業が再始動 7月の訪日中止を経て正常化へ
日中の軍事交流事業は2001年に開始され、日本側は笹川平和財団、中国側は中国国際戦略学会が窓口となってきた。中国軍代表団は本来、今年7月に訪日する予定だったが、「日程調整がつかない」として中止された。
背景には、7月に太平洋上空で中国軍機が自衛隊機に異常接近した事案や、海上自衛隊護衛艦の台湾海峡通過など、軍事的緊張の高まりがある。対話の停滞が続くなかで今回の訪中が実現したことは、制度的交流が再稼働したことを意味する。
東アジアでは、米軍が日本国内で初公開した「タイフォン」ミサイルをめぐり、中国が撤去を要求するなど、軍備を巡る緊張が継続している。(関連:「米軍タイフォン、日本で初公開」 https://www.alertchina.com/post-32886/)。こうした情勢は、日中の危機管理対話の必要性を押し上げている。
小泉防衛相と董軍国防相の初会談 安保対話の基盤強化へ
自衛隊幹部の訪中に先立ち、日本の小泉進次郎防衛相と中国の董軍国防部長は11月1日にマレーシア・クアラルンプールで初の防衛相会談を実施した。会談では、防務分野の全レベルでの対話強化、海空の偶発的衝突を防ぐ危機管理メカニズムの改善などが協議された。
台湾海峡や東シナ海の情勢が不安定化し、米中関係も揺れるなか、日本と中国の防衛当局間の意思疎通は地域の安定にとって欠かせない。今回の訪中は、対話の“実働レベル”を回復させる試金石といえる。
地域情勢の緊張と対話再開の意義 “安全保障再構築段階”に入る日中関係
今回の自衛隊幹部訪中は、首脳会談・防衛相会談と連携した具体的措置であり、日中が安全保障対話の「再構築段階」に入ったことを示している。軍事交流の再始動は、象徴的措置以上の意味を持ち、情報共有や偶発的衝突の抑止など実務的効果が期待される。
中国が軍近代化を加速し、日本が防衛力を強化するなか、両国の意思疎通は東アジア情勢の安定に直結する。日本国内では米軍「タイフォン」の配備が議論を呼び、中国側は日本の外交姿勢への警戒を強めている。両国の関係改善には、定期的な対話枠組みの維持が不可欠だ。
国際社会も、今回の訪中を東アジアの危機管理における重要な進展として注視している。
[出典]
・中央社:https://www.cna.com.tw/news/acn/202511050426.aspx
・東網 on.cc:https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20251106/bkn-20251106101154851-1106_00822_001.html