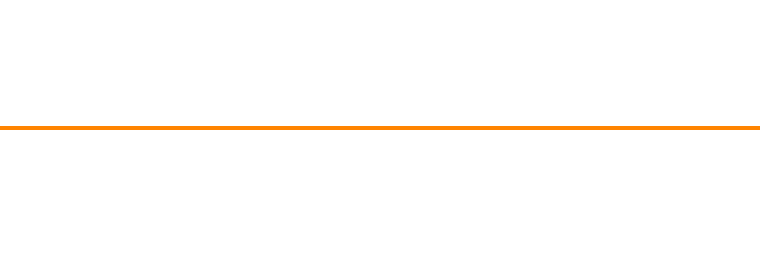広東省汕尾市で94人の児童が搬送

9月11日、広東省汕尾市陸豊市の普寧華美実験学校小学校部で児童が相次いで体調を崩し、94人が病院へ搬送された。症状は腹痛や嘔吐など典型的な食中毒のものだった。保護者によると、昼食で提供された鶏手羽が十分に火が通っておらず、子どもが「生焼けだった」と話していたという。
この地域では過去にも食の安全に関わる事件が起きており、特に食品管理の不備に関する報道は繰り返し問題視されてきた。今回も学校側が当初「体調不良」とだけ説明して食中毒を否定したため、保護者の間で不信感が強まり、隠蔽の疑念が噴出した。
山東省済寧市では138人の生徒と教員が症状
翌12日には山東省済寧市兗州区の朝陽育才中学で集団食中毒が発生し、138人の生徒と教員が搬送された。当日の夜10時までに全員が経過観察となり、症状はいずれも軽症とされた。
保護者の証言によれば、校外業者が一括配送したハンバーガーを食べた直後に異常が出たとされる。SNS上では「味に異常があった」との証言もあり、拡散した映像には生徒が廊下で倒れ込む姿が映っていた。こうした映像や証言は、過去に学校の管理体制に疑問が投げかけられた事例とも重なる。
当局の対応と合同調査チームの設置
教育局は食品サンプルを採取し、仕入れルートや加工工程の検査を開始した。兗州区では教育・衛生健康・市場監管の各部門から成る合同調査チームを設置し、診療と原因究明を進めている。
しかし一方で、保護者が事件の経過を抖音に投稿したところ学校側から削除を求められたという証言もある。さらにネット上には学校を擁護する記事が多数出回り、火消しの疑いも持たれている。こうした情報統制の動きは、以前の教育現場での情報公開に関する問題とも共通点を持っている。
社会的反響と食品安全への不信
2件の事件で計230人以上が搬送され、社会的関心が一気に高まった。いずれも軽症で済んだものの、学校給食や外部配送食品の安全性に対する不信は強まっている。特に中国では過去にも繰り返し食中毒事件が発生しており、そのたびに市民の安全を揺るがす事例として波紋を広げてきた。
今回の事件は、食品管理体制の不備だけでなく、学校や当局による情報公開の姿勢が問われる形となった。透明性の欠如は市民の不安を拡大させ、再発防止への期待を損なう。社会全体として食品安全をめぐる信頼回復が急務である。
関連ニュースと今後の課題
過去にも学校や公共施設で発生した集団中毒は繰り返し報告されており、例えば地域社会での安全対策に関する取り組みも議論されてきた。今回の広東・山東の事件は、食品安全と教育現場の危機管理を改めて見直す契機となる可能性がある。
外部リンク:出典の確認
今回の事件については、以下の外部メディアも詳しく報じている。
東網(on.cc):「疑集體食物中毒 汕尾近百小學生送院」
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20250913/bkn-20250913131431320-0913_00822_001.html
中央社(CNA):「中國中小學校園頻傳食物中毒 連續2天逾230人送醫」(2025年9月14日)
https://www.cna.com.tw/news/acn/202509140181.aspx
香港01:「山東學校多名師生嘔吐肚痛 家長懷疑食物中毒 當局展開調查」
https://www.hk01.com/即時中國/60276070
星島頭條(StHeadline):「食漢堡包出事?山東一學校爆集體食物中毒 138師生求診逼爆醫院」
https://www.stheadline.com/realtime-china/3499069
結論
広東と山東で発生した2件の食中毒事件は、短期間に230人以上を病院へ搬送させ、学校給食や外部配送食品の管理体制に深刻な疑問を投げかけた。原因究明と厳格な責任追及はもちろん、透明性のある情報公開と持続的な安全管理体制の確立が今後の最大の課題となる。